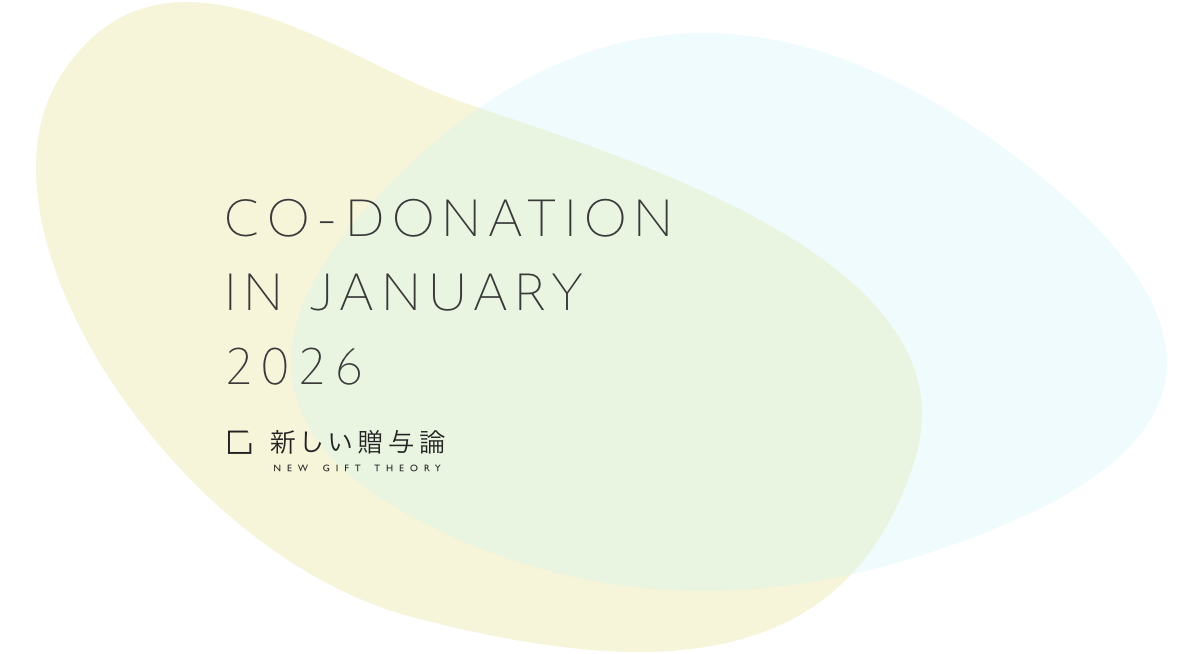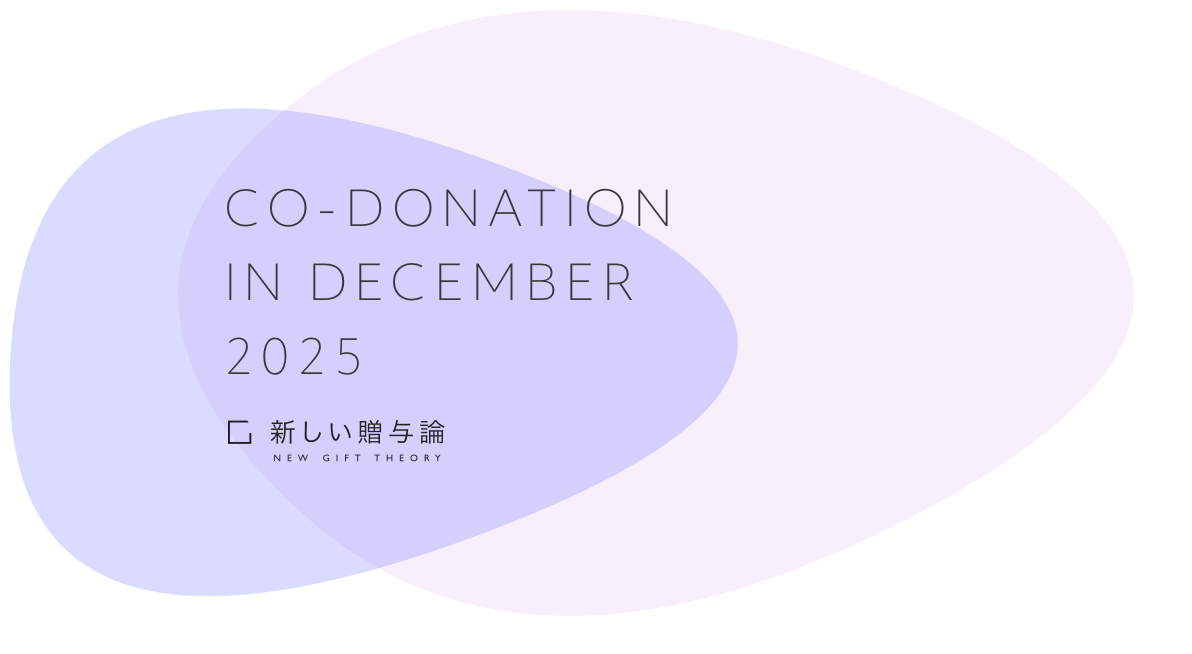新しい贈与論は、公益社団法人Marriage For All Japanに87.5万円の寄付を行ないました。
新しい贈与論では毎月会員の投票により宛先を決定する共同贈与を行なっています。今月は「クィア」をテーマに推薦を募集し、「株式会社クーゼス」「新人Hソケリッサ!」「公益社団法人Marriage For All Japan」の3候補があがり、横山詩歩・佐伯ポインティの推薦した公益社団法人Marriage For All Japanが最多票を得ました。
推薦文は以下の通りです。
https://www.marriageforall.jp/
30代に差し掛かり、自分の周りでも「結婚したいかどうか」についての話題が増えてきました。
先の見えない時代に不安を感じて「将来孤独になりたくない、だから結婚しておきたい」と思う人もいれば「結婚するより、自分1人で生きていく方向で考えたい」という人もいます。
また、30代半ばを迎えたもう一人の推薦人の周りでは、結婚はしないと話していた人が、子どもの親権を得るためには結婚が必要だと判断したり、外国籍のパートナーが病気になった時の在留資格に備えて結婚を選択するという話を聞くこともありました。
結婚するかどうか──この問いは、長い人生を生きていくことを考える上で、多くの人が考え立ち止まる難所であるはずなのに、そもそも結婚すること自体が国に認められていない同性愛者の人は、その二択で悩むことすらできない。現代に根強く残る、明らかな差別です。同性婚はどの生も排除されないための一つの選択肢。結婚する自由も、しない自由も、同じだけ尊重される社会が目標です。
そしてこの同性婚の実現に向けて、他に類を見ない動きをしているのが、Marriage For All Japan です。
この団体は、イベントやセミナー、ロビイングに留まらず、「結婚の自由をすべての人に」訴訟・PRをサポートもしているんです。札幌・東京・名古屋・大阪の4つの地方裁判所で一斉に訴訟を開始した後、福岡の地方裁判所でも訴訟を起こしました。
「訴訟」と聞くと、ぎょっとするかもしれませんが、この訴訟は、"法律上の性別が同じカップルが結婚できないことが憲法違反だと正面から問う、日本で初めての訴訟"なのだそうです。すごいですよね、日本の婚姻制度の歴史を変えようとしている重要な局面ですから、そりゃ訴訟も必要です。
結婚したからこそ、できることは多いです。パートナーの急病に面会したり、共同でローンを組んだり、相続をしたり…思うに、結婚と贈与は分かちがたく結びついています。なので、そもそも結婚することを認められていない人たちがいる現状に対して、その解消をサポートすることが、ひいては包括的な贈与に繋がるのではないかと思いました。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2025年12月11日に最高裁判所に上告し、今後は最高裁で闘っていくことになるそうです。そこをぜひ贈与論で寄付をして訴訟の実費として支援したいと思い、推薦いたしました。
投票にあたり会員よりあがった理由の一部を抜粋し紹介いたします。
結婚する自由も、しない自由も、同じだけ尊重されますように。(横山詩歩)
最高裁の判断がどうなるのかはわかりませんが、同性婚の法制化は避けては通れないと思います。(清水康裕)
関心の強い順に選び、特に最近ニュースでもよく見かける同性婚を支援するMarriage For All Japanを第一希望としました。(栖原志歩)
社会的インパクトが大きそうなため(日吉良太)
マリフォーさんは国会議員の同性婚に対する態度の可視化などを含めて、市民活動のあり方として勉強になる点が多かったのが決め手でした。BSを見ると資金体力は比較的ある印象でしたが、それでもマリフォーさんに入れます。(中村祥眼)
「結婚の自由を全ての人に」を実現するため、迷いなく寄付したいと思いました。(古賀翔子)
全ての人に多くの選択肢がある社会になってほしいから。(漢那宗泰)
同性婚を法制化することは人権擁護の観点からも、またすべての人が等しく個として尊重される社会を構築していく上でも、とても重要なポイントになると確信しています!マリフォーさんのアドボカシーが実を結ぶことを祈り、支援をしたいと思います!(坂本治也)
基本的な選択肢の平等に向けての活動であるという点に惹かれました。(加藤めぐみ)
今回も迷ったが、社会の変革を起こすのに最も有効そうに感じたMarriage For All Japanを選んだ。(高城晃一)
包括的な贈与に繋がるという推薦文に対してその通りだなと感じましたので、投票させていただきます!(鈴木弘人)
率直に一番応援したいと思いました!得られる喜びと、和らぐ苦しみの、総量の観点でマリッジフォーオールを選びました。推薦理由は推薦人の文章に書いた通りです。(佐伯ポインティ)
今このタイミングで寄付する先として、公益社団法人Marriage For All Japanを選択しました。これからの訴訟のパブリックビューイングのチケットを手に入れるような気持ちで、同性婚の問題と関わるきっかけにしたいです。(秋山福生)
すぐに変わることはないかもしれませんが、この寄付が日本の社会を変える一歩につながると信じて。(市村彩)
新しい贈与論は今後も共同贈与という形の寄付を毎月続けて参ります。ご興味のある方はぜひご参加ください。
運営
法人名 一般社団法人新しい贈与論
代表理事 桂大介
設立 2019年8月1日
ウェブサイト https://theory.gift
連絡先 info@theory.gift
メディアキット ダウンロード
「新しい贈与論」は寄付や贈与についてみなで学び、実践してゆくコミュニティです。オンラインの交流をベースに、時折イベントや勉強会を開催します。個人主義や交換経済が蔓延り、人間や人間的関係がますます痩せ細ってゆく現代において、今一度、贈与という観点から社会について考え行動する場をつくりたいと思います。